 |
||||
ブリンズリー・シュウォーツというバンドを最初に知ったのはいつのことだっただろうか。渋谷は百軒店にあったロック喫茶ブラックホークだったか、それとも高田馬場のレコード・ショップOpus Oneだったかはもう定かではないが、確か78〜79年頃のことだったと思う。バンドの筆頭格であるニック・ロウは既にソロ・アクトへと転じ、スティッフやレイダーといった新興インディ・レーベルからガンガンとシングルをリリースしていた、そんなニュー・ウェイヴが台頭していた時代だった。ニックは当時プロデューサーとしてもグレアム・パーカー、ダムド、そしてプリテンダーズなどを担当し、まさに飛ぶ鳥を落とすような勢い。そう、時代はヒッピーからパンクスへ。ロンゲから短髪へ。例えば道玄坂のシカゴでブーツカットのジーンズを買うのも躊躇われるほどだったと記憶する。
バンド名として冠するにはあまりに冴えないというか、マーケッティングという概念が隅々にまで行き届いた現在であればプレゼンにすら量れない。そんなブリンズリー・シュウォーツという名前が、このバンドのギタリストの個人名だと知った時の何とも腰が抜けるようなトホホ感は、やがて親愛の情へと変わっていった。グループ名を考えるのが単にめんどくさかったのか、あるいは照れがあったのかは知る由もないけれども、そうしたことには無頓着というか、むしろ演奏をずっと続けられればそれでいいとでも言いたげな邪心のなさすら感じ、ぼくは次第にこの英国バンドを好きになっていった。
グループの結成は69年。前身となるキッピントン・ロッジは67年にパーロフォン・レーベルからデビューしたサイケ・ポップ的なバンドだったが、そこに在籍していたブリンズリー・シュウォーツ(g,vo)の元へとニック・ロウ(b,vo)、ボブ・アンドリュース(kbd,vo)そしてビリー・ランキン(ds)が次第に合流し母体が築かれ、UAレーベルと契約した。マネージャーのデイヴ・ロビンソンがまず画策したのは、多数のメディア関係者たちを引き連れてアメリカに上陸し、デビューを派手に持ち上げるというものだった。ヘッドライナーにクィックシルヴァー・メッセンジャー・サーヴィスとヴァン・モリソンを迎え、フィルモア・オーディトリアムで行われたデビュー・コンサートはしかしながら大失敗に終わってしまう。彼らはこの時に抱えた負債を返すためイギリスに戻り、タリー・ホーやホープ&アンカーなどロンドン各地のパブ・サーキットで演奏するようになったのだ。ブリンズリーズはのちにパブ・ロックの開祖と呼ばれるようになったが、彼らにしてみればこんな屈辱的な出発点があったのである。
しかしそれでも表の流行シーン(例えば当時であればT.レックス、デヴィッド・ボウイ、ロキシー・ミュージックなどのグラム・ロック)とは無縁のパブという裏街道で育まれたのは、カントリーやR&Bなどのルーツに根ざしたアメリカ音楽への眼差しであり、毎晩の如く酔客たちを相手にしながら鍛えられた柔軟な演奏力だった。ちょうど米サンフランシスコから渡英していたクローヴァーやエッグス・オーヴァー・イージーといったアメリカのバンドとの交流もまた刺激になったことだろう。ちなみにクローヴァーにはのちに大ブレイクするヒューイ・ルイスや、ドゥービー・ブラザーズに参加するジョン・マクフィーが、エッグスにはオースティン・デ・ローンが在籍していた。のちにエルヴィス・コステロがニック・ロウのプロデュースで最初のアルバムを作った際、バッキングをクローヴァーが担当したのは、このような背景があったからだ。デ・ローンにしてものちにコステロの作品やツアーに抜擢されたことがある。ここら辺の連携はまさにパブの絆といったところだろうか。
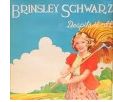
 話をブリンズリーズに戻そう。彼らの最初の2枚のアルバム『Brinsley Schwarz』と『Despite It All』(ともに70年発売)ではまだまだCSN&Y流フォーク・ロックからの影響が強く、また『Despite It All』のジャケット(青空と少女の絵柄)は容易にイッツ・ア・ビューティフル・デイ69年のデビュー作のそれを思わせるものだったが、72年に発表されたサード・アルバム『Silver Pistol』の頃になるとザ・バンドへの憧れからか、よりアーシーなサウンドを身に付けるようになった。カーサル・フライヤーズのウィル・バーチの言を借りれば「ナイーヴな魅力に溢れ、かつ繊細なダウンホーム感覚とドゥ・イット・ユアセルフな質感を備えた」アルバムだった。メンバーの持ち家に8トラックの機材を持ち込んで録音されたのも、ザ・バンドがサミー・ディヴィス・Jrの邸宅を借り切ってレコーディングされた通称〝ブラウン・アルバム〟の神話に倣ってのことだったに違いない。
話をブリンズリーズに戻そう。彼らの最初の2枚のアルバム『Brinsley Schwarz』と『Despite It All』(ともに70年発売)ではまだまだCSN&Y流フォーク・ロックからの影響が強く、また『Despite It All』のジャケット(青空と少女の絵柄)は容易にイッツ・ア・ビューティフル・デイ69年のデビュー作のそれを思わせるものだったが、72年に発表されたサード・アルバム『Silver Pistol』の頃になるとザ・バンドへの憧れからか、よりアーシーなサウンドを身に付けるようになった。カーサル・フライヤーズのウィル・バーチの言を借りれば「ナイーヴな魅力に溢れ、かつ繊細なダウンホーム感覚とドゥ・イット・ユアセルフな質感を備えた」アルバムだった。メンバーの持ち家に8トラックの機材を持ち込んで録音されたのも、ザ・バンドがサミー・ディヴィス・Jrの邸宅を借り切ってレコーディングされた通称〝ブラウン・アルバム〟の神話に倣ってのことだったに違いない。 耳を澄ませば犬の鳴き声さえ聞こえてくるこの『Silver Pistol』は、細野晴臣の『Hosono House』やジェイムズ・テイラーの『One Man Dog』同様にホーム・レコーディング・アルバムの指標のひとつなのかもしれない。また『Silver Pistol』からは五人めのメンバーとしてイアン・ゴム(g, vo)が加わり、ソングライティングやバンド・アンサンブルに膨らみが増したことも聞き逃せまい。
耳を澄ませば犬の鳴き声さえ聞こえてくるこの『Silver Pistol』は、細野晴臣の『Hosono House』やジェイムズ・テイラーの『One Man Dog』同様にホーム・レコーディング・アルバムの指標のひとつなのかもしれない。また『Silver Pistol』からは五人めのメンバーとしてイアン・ゴム(g, vo)が加わり、ソングライティングやバンド・アンサンブルに膨らみが増したことも聞き逃せまい。
 72年の秋に発売された『Nervous On The Road』も『Silver Pistol』と響き合う The Band ライクな彫りの深い音像が魅力的なアルバムだった。4作めにしてやっとメンバーの顔が表ジャケットに大写しとなったが、当時彼らのローディをしていたマーティン・ベルモント(のちにダックス・デラックスからザ・ルーモア、そしてニック・ロウのカウボーイ・アウトフィットヘ)が中央に写っているという鷹揚さ。こうしたファミリー的な結束感もまた彼らの良さだろう。なおレコーディングには初めてウェールズのロックフィールド・スタジオが選ばれ、当スタジオの主であるチャールズ&キングスレー・ワード兄弟の片割れであるキングスレー・ワードがプロデュースに加わっている。ワード兄弟とともにロックフィールド・スタジオでエンジニア技術を習得したのが言わずと知れたデイヴ・エドモンズだが、彼とブリンズリーズとの接点は恐らくこの頃から生まれたと思われる。
72年の秋に発売された『Nervous On The Road』も『Silver Pistol』と響き合う The Band ライクな彫りの深い音像が魅力的なアルバムだった。4作めにしてやっとメンバーの顔が表ジャケットに大写しとなったが、当時彼らのローディをしていたマーティン・ベルモント(のちにダックス・デラックスからザ・ルーモア、そしてニック・ロウのカウボーイ・アウトフィットヘ)が中央に写っているという鷹揚さ。こうしたファミリー的な結束感もまた彼らの良さだろう。なおレコーディングには初めてウェールズのロックフィールド・スタジオが選ばれ、当スタジオの主であるチャールズ&キングスレー・ワード兄弟の片割れであるキングスレー・ワードがプロデュースに加わっている。ワード兄弟とともにロックフィールド・スタジオでエンジニア技術を習得したのが言わずと知れたデイヴ・エドモンズだが、彼とブリンズリーズとの接点は恐らくこの頃から生まれたと思われる。

 以降ブリンズリーズは『Please Don't EverChange』(73年)『New Favourites Of Brinsley Schwarz』(74年)といずれも評価の高いアルバムを続々とリリースしていく。前者ではヴィック・メイル(のちにドクター・フィールグッド、パイレーツ、モーターヘッドを制作)がプロデューサーとして初登場し、後者では遂にデイヴ・エドモンズに制作を仰ぐなど、サウンドにより磨きを掛けていった。デイヴとニック・ロウとの友情の始まり(二人はのちにロックパイルを結成)を感じさせるのも『New Favourites Of.....』の特徴だろう。この直後に発売されたデイヴ2枚めのソロ『Subtle As A Flying Mallet』(75年)にも、ニックやボブ・アンドリュースなどブリンズリー・チームが参加していたからだ。ロックフィールド・スタジオで録音されたこの2枚を地続きの兄弟作として聞き直してみると、デイヴやニックの音楽趣味(フィレス・サウンド、R&B、初期のロックンロールからフィラデルフィア・ソウルまで)がより鮮明に浮かび上がってくるような気がする。75年には最終作として『It's All Over Now』が録音されたものの、これは残念ながらテスト盤が僅かにプレスされただけで終わり、バンドは75年の3月18日、マーキー・クラブでのステージを最後に終焉の時を迎えた。わずか5年余りの活動期間だった。
以降ブリンズリーズは『Please Don't EverChange』(73年)『New Favourites Of Brinsley Schwarz』(74年)といずれも評価の高いアルバムを続々とリリースしていく。前者ではヴィック・メイル(のちにドクター・フィールグッド、パイレーツ、モーターヘッドを制作)がプロデューサーとして初登場し、後者では遂にデイヴ・エドモンズに制作を仰ぐなど、サウンドにより磨きを掛けていった。デイヴとニック・ロウとの友情の始まり(二人はのちにロックパイルを結成)を感じさせるのも『New Favourites Of.....』の特徴だろう。この直後に発売されたデイヴ2枚めのソロ『Subtle As A Flying Mallet』(75年)にも、ニックやボブ・アンドリュースなどブリンズリー・チームが参加していたからだ。ロックフィールド・スタジオで録音されたこの2枚を地続きの兄弟作として聞き直してみると、デイヴやニックの音楽趣味(フィレス・サウンド、R&B、初期のロックンロールからフィラデルフィア・ソウルまで)がより鮮明に浮かび上がってくるような気がする。75年には最終作として『It's All Over Now』が録音されたものの、これは残念ながらテスト盤が僅かにプレスされただけで終わり、バンドは75年の3月18日、マーキー・クラブでのステージを最後に終焉の時を迎えた。わずか5年余りの活動期間だった。
ブリンズリーズの音楽性を彼らがカヴァーした曲から探っていくのも面白いだろう。P.J.プロビーでヒットした「Niki Hoeke Speedway」(67年2月に全米で23位)を手始めに、クリス・ケナーのニューオーリンズR&B「I Like It Like That」(61年7月に2位)、ゴフィン=キングが書き下ろしたクリケッツ63年の「Please Don't Ever Change」に関しては、アメリカのチャートには入らず英国のみでヒットした曲を採用する思い込みを伺わせていた。ニューヨーク出身のR&Bクィンテットであるキャデラックスの「Speedo」(56年7月に15位)は、ヤングブラッズやライ・クーダーのヴァージョンでお馴染みの方も少なくはないだろう。ブレンダ・リーやジェリー・リー・ルイスに曲を提供していたロカビリー・シンガー、ロニー・セルフの「Home In My Hand」はスタジオとライヴそれぞれのヴァージョンを異なるアルバムに収録した。また一方でボブ・マーリィ&ウェイラーズがロックステディの時期に吹き込んだ「Hypocrite」に関しても、レゲエ・シングルAB面の通例に倣ってヴォーカル版とヴァージョン(カラオケ)版の両方を、やはり違うアルバムごとに聞かせるという念の入れようだった。こうした遊び心というか茶目っ気は、ニック・ロウがソロになって全開させる類のものである。ブリンズリーズにとっては母国の先輩格であるホリーズの「Now The Time」の粋な響きや、オーティス・クレイのメンフィス・ソウル「Trying To Live My Life Without You」のポンコツな解釈も思わず笑みを誘うものだった。蛇足として加えるのならば、発売が見送られてしまった幻の最終作ではボビー・ウーマック&ヴァレンチノズの「It's All Over Now」(ローリング・ストーンズ版が64年の8月に26位)や、ウィリアム・ベル&ジュディ・クレイのスタックス曲「Private Number」などをブートレグCDで聞くことが出来る。この世に出ることがなかったとはいえ、クォリティがとても高い作品だけに、いつの日にか正式にリイシューされることを願って止まない。
ニック・ロウのソングライティングについては、その才を誰もが認めるところだろう。ブリンズリーズの初期に生まれた「Country Girl」や「Love Song」の柔らかな旋律は今なお新鮮だし、ザ・バンドへの憧憬は「The Slow One」や「Brand New You, Brand New Me」での含蓄のあるサウンド絵画からも十分に汲み取れる。ヴォーカリストとしてはブラック・ミュージック的な押し出しの強さよりも、カントリー・ライクな味わいに真価を発揮するタイプだ。そして特筆すべきは、計らずも代表曲となってしまった解散間際の「(What's So Funny 'Bout) Peace Love And Understanding」に関するエピソードだろう。表題にあるような〝平和と愛と理解〟をそのままストレートに賛美する歌ではなく、ここには彼特有の苦みや皮肉が込められていたのだった。
ウィル・バーチの著作『No Sleep To Canvey Island』(以前シンコー・ミュージックから翻訳版が『パブ・ロック革命』として出た)でニック・ロウはこう振り返っている。「あの頃のぼくが多くの時間とエネルギーを注いできたあのヒッピーってやつは、すっかり古臭くてナンセンスなものへとなっていった。ぼくはそれが廃れていく様をずっと見てきた。そして頭のなかでこう考えたのさ。どこかの年老いたヒッピーがこう言うんだ。〝今すべてが変わろうとしている。きみは笑うかもしれないが、だからといって平和と愛のいったいどこがそんなに可笑しいというんだい?〟 ぼくはちょっとばかりの皮肉を込めてあのイカしたリリックを入れたのさ。もちろん平和と愛っていうのは基本的にはいいことだと思うよ。でも突然昔の夢が終わって、ぼくは今まさに、(バンド解散間際の)この場所に立っているんだ。何かに気が付くためにね。ある意味でこいつは目覚めのための歌なんだ」
自らを時代に取り残されていく老人に譬えながら「平和と愛と理解のどれがそんなに可笑しいんだい?」と歌ったニック・ロウの心模様はどれほどのものだっただろうか。逆にこの曲のエルヴィス・コステロ版は怒れる若者といった疾走感をストレートに表出させたものへと生まれ変わっている点が大いに興味深い。いずれにしても、冒頭で触れたように75年前後を機にヒッピー・ロックの時代は幕を下ろし、パンクやニューウェイヴのムーヴメントが到来する。そんな意味でニック・ロウはあの懐かしいヒッピー・カルチャーとパンク〜ニューウェイヴ旋風という両方の時代を目撃してきた生き証人のような存在かもしれない。ニックが抱えたそんな屈折や毒気は、例えば彼のデビュー・アルバムが『クールの神様』(Jesus Of Cool)と冠されていたこと、さらにその冒頭曲が「音楽は金さ!」(Music For Money)であったことにもよく現れている。なお余談だが米国ではジーザスという言葉が引っ掛かったのだろうか、アルバム表題は『Pure Pop For Now People』というものに改められている。
 最後にとっておきの美談を。件の「(What's So Funny 'Bout ) Peace Love And Understanding」はのちにケヴィン・コスナーとホィットニー・ヒューストン主演のメガ・ヒット映画『ボディーガード』(92年)でカーティス・スティガーズのヴァージョンによって挿入され、作者のニック・ロウに相当の印税をもたらした。イギリスだけでサウンドトラック・アルバムを29万枚売り上げたというからその金額は推して然るべしだろうが、ニックはその印税をかつてのバンド・メイト、つまりブリンズリーズの面々へと分け与えたという。ニックはこう回想している。「ブリンズリー・シュウォーツのメンバーで、今もフルタイムで音楽をしているのはぼくだけじゃないのかな?」そこに込められた自尊心とある種の痛みが近年の彼の音楽をより味わい深いものにしている。ニック2011年の最新作『This Old Magic』に収録された「House For Sale」のエンディング間際でも彼は〝Peace, Love And Understanding〟の一節をまるで去り行く男のように呟いているのだから、ニックにとってもこの曲は勲章であると同時に、作者の意図を離れて広く大衆のものとなった足枷なのかもしれない。そんな切ない気持ちまでブリンズリーズの音楽は今日もなお運び込んでくるのだった。(了)
最後にとっておきの美談を。件の「(What's So Funny 'Bout ) Peace Love And Understanding」はのちにケヴィン・コスナーとホィットニー・ヒューストン主演のメガ・ヒット映画『ボディーガード』(92年)でカーティス・スティガーズのヴァージョンによって挿入され、作者のニック・ロウに相当の印税をもたらした。イギリスだけでサウンドトラック・アルバムを29万枚売り上げたというからその金額は推して然るべしだろうが、ニックはその印税をかつてのバンド・メイト、つまりブリンズリーズの面々へと分け与えたという。ニックはこう回想している。「ブリンズリー・シュウォーツのメンバーで、今もフルタイムで音楽をしているのはぼくだけじゃないのかな?」そこに込められた自尊心とある種の痛みが近年の彼の音楽をより味わい深いものにしている。ニック2011年の最新作『This Old Magic』に収録された「House For Sale」のエンディング間際でも彼は〝Peace, Love And Understanding〟の一節をまるで去り行く男のように呟いているのだから、ニックにとってもこの曲は勲章であると同時に、作者の意図を離れて広く大衆のものとなった足枷なのかもしれない。そんな切ない気持ちまでブリンズリーズの音楽は今日もなお運び込んでくるのだった。(了)
(c) Obi Takashi - Sakatomi Design