Page 1 < > page 2 |
||||||
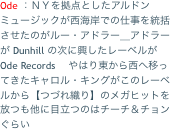 |
||
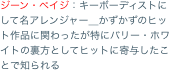 |
||
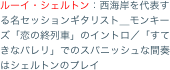 |
||
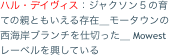 |
||
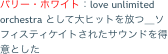 |
||
 D:デヴィッドTは… Ode* じゃない。てか、オードのセッションバックが多かったけどソロも…だよねえ?
D:デヴィッドTは… Ode* じゃない。てか、オードのセッションバックが多かったけどソロも…だよねえ?
U:ソロは71年ですね。ただ、前に(本人に)聞いたことがあるんですけど、最初のオードでの仕事はペギー・リプトンのセッションだと。LPが出たのは69年で…でも、そこからは聞こえてこないんですよね、デヴィッドTらしいギターが。で、アルバム未収録のシングルオンリーが何曲かあって、そのうちの1曲で聞こえるんですね…なのでこれのことなのかなあ、と。
D:なるほど。じゃあその前のセッションワーク…オード以前というのは?
ところでデヴィッドTはどこの生まれ?
U:オクラホマですね。生まれてすぐにロスへ移っているらしいので基本はずっとロスの人です。
D:最初の仕事は…モータウンといったっけ?
U:そこのところが複雑なんですよ。巷で言われるのがデヴィッドは「モータウン専属ギタリストであった」なんです。でもホントはそうじゃなくて、モータウンと契約したのはマーサ&ヴァンデラスのツアーバンド、あくまでツアーのバックバンドだったそうです。それもデヴィッドTひとりじゃなくて…。当時彼はキンフォークス*というバンドをやっていて、その解散と同時にそこからメンバー三人がバックバンドとして契約、そのなかにデヴィッドも含まれていたんですね。
あくまでひとつのグループのツアー仕事を契約しただけで、実はモータウン全体とのバックギタリスト契約なんてものは端から無かったそうです。
D:あ、そう。
U:それが67年のことで、レコードとして残っているのがヴァンデラスの唯一のライヴ盤なんです。
D:そこではデヴィッドTのギターは聴けるの?
U:ええ、もうその時からばりばりにデヴィッドTなんです (笑)。実はそのバックのままで日本に初めて来ています。68年なんですけど、モータウンのパッケージツアー…スティーヴィー・ワンダーとマーサ&ヴァンデラスの二組で来日公演を行ったんですね。当時にデヴィッドTを知っていた日本人はいなかったでしょうけど。新宿でスーツを買ったんだと言ってました (笑)。それから80年代にクルセイダーズで来るまではまったく来日はなかったんです。
D:そのヴァンデラスのツアー仕事ってのは西海岸を回っただけ?
U:いや、ニューヨークでもやったようなので全米を回ったんじゃないかな。
D:そうか、なかにジャパンもありってことね。…そのツアーでの仕事ぶりが認められて録音へも、他のアーティストのセッションへも誘われるようになったのかな?
U:え〜と、ヴァンデラス仕事をやりつつもソロを出す機会を得るんです。モータウンとは違うレーベルから。アルバムは68年に出ます、ファーストソロですね。翌69年にはセカンドソロも出ます。ちょうどその頃が、さっきのペギー・リプトン仕事ですね。つまりルー・アドラーと知り合うんです。ジーン・ペイジ*とも知り合う。同時期、69年にジャクソン5のファーストが出るんですよね。例の"I want you back"でデヴィッドはギター参加するんです。ただ、マーヴィン・ゲイの63年のアルバムセッションに参加しているので正確にはそれより以前にモータウンアーティストと仕事はしているんです。でも、本格的に、という意味では、68年から69年にかけてがモータウン・セッションの始まりだった。モータウンがデトロイトからロスに移ってくる時期と重なっていることもあって、時系列では実際どうだったのか、この辺りホント面白く興味深いところなんですけどね。
D:なるほどねえ。オード仕事とモータウン仕事がからんで忙しくなってきたわけだな。オードはもちろんだけど、ジャクソン5の録音などもロスだったのかな?
U:ほとんどロスだったと思います。
D:"ABC" のイントロはルーイ・シェルトン*じゃない。シェルトンはジャクソン5でかなり弾いているみたいだよね。
U:"ABC"の話でいうと、最近のライブでもデヴィッドはこの曲のサビのフレーズを「ジャクソン5メドレー」みたいな流れの中でプレイすることがあるんです。でも、レコードではそのフレーズは聴きとれないんですよね。デヴィッド本人はこの曲のセッションに参加したと明言してるので事実だと思うんですけど。ただお皿になっている音は微妙で、メインのフレーズからデヴィッドの音がはっきりとは聴き取れない。この例に限らず、レコーディングのときに何テイクも録ったけど、最終的に差し替えられたっていうケースはあると思うんですよね。どれが使われたか本人は知らないことのほうが多いっていう。
D:そこらって、微妙だよね。
セッションギタリストってギャラもらって短時間ギターを弾くだけが仕事じゃない。でもそのテイクの採用に関わっちゃいないわけだから、本人でも後でレコードを聞いて「あれ、ギャラもらったのにオレのギター聞こえないなあ」なんてよくあるだろうしね。ましてクレジットの無かった60年代では記憶だけが頼りだしね。
70年代、クレジットが入る時代になっても…だいたいは信用しているけど完全じゃないよね。録音が完全に済んでからうろ覚えでクレジット入れている盤もあるように思える。
U:セッションには呼んだけれど使えるテイクは無かった…しかしせっかく弾いてもらったんで名前は入れておくなんてことも…あったかもしれないですよね。その場合はギャラは支払われるわけですから、本人の記憶と音源が一致しないこともありそうな…。
D:まあ古い話だし、完璧にメンツの解明なんて不可能なことだよね。結局は耳だけが拠り所なわけで…。
U:そうですね。自分で聴いて思うところが正解でしょうね。
D:西海岸と東海岸、まあロスとNYとして…その距離感がいまひとつオレはつかめないんだなあ。
一枚のアルバムのためのセッションがどちらでもあったとして、ロスのデヴィッドTはほいほいとすぐにNYまで飛んだんだろうか、とかね。日帰りできたことなのかとかも。結構距離有ると思うけど、飛行機使えばなんでもなく出張気分で行き来する距離なのかなあ…。
U:僕は…それも可能かもしれないけれど、なんとなくデヴィッドTの場合はない気がしますね。やっぱりロスがほとんどだろうと。
D:う〜ん、そうねえ、距離だけじゃないしね。機材の運搬の問題もあるか…。
D:オードでのデヴィッドTというとオレのなかでは…キャロル・キングの【fantasy】なんだな。SSW然としていたあのキャロルなのにこの新譜はソウルジャズ系のバックが付いての録音! 、みたいな話題にもなったと思う。デヴィッドTにハーヴィ・メイスンでしょ。ベース誰だっけ?
U:チャールズ・ラーキーです。
D:あそうか、旦那ね。まあデヴィッドTでも白人のバックが有りなのねと思わせた盤があれだったかなあ。
U:僕もそんな気はします。
D:君がサイトであれだけデヴィッド参加盤を採り上げているけれど、こういうのも有りか、このバックもやるのか…そういう意外な参加というのもあるわけでしょ?
U:人脈のことが…ありますかね。ジーン・ペイジと一緒にやる、HBバーナム*とはよく仕事したとかあるんですよ。で、九割方はそういう「からみが見える」盤なんですね、デヴィッドTの場合。ただそうじゃない盤が少しあるんですよ。どうしてここで弾いているんだろうという盤が。ほとんどがマイナーなレコなんで気にする人はいないでしょうが…。
ちょっと話逸れますが、モータウン人脈というとハル・デイヴィス*がポイントだと本人は僕に言ってくれましたね。
D:ほうほう、モータウンのなかでひいきにしてくれた人…という意味でハルがいたのかな。
U:よくジーン・ペイジとのコンビと言われるデヴィッドTなんですが、たしかにクレジットも多いです、ふたり揃っているのが。でも元をたどればハル・デイヴィスがジーン・ペイジをピックアップしていたというケースもあったと思うんです。
D:オードのほうはやっぱりルー・アドラーが…?
U:そうでしょうね。
D:かなり信頼関係ができていた感じ、するよね。オードのセッションならデヴィッドにはかならず一声かけるみたいな…。
U:ええ。ただ中にあるんですよ、なぜこの盤に参加してないの? というのも。同じオード所属ってことでいうと、トム・スコットのソロ盤とか。キャロル・キング盤ではレコーディングも一緒だしツアーも一緒にやっていたんですけどね。
D:トム・スコットといえば…彼はギタリストじゃないけれど、デヴィッドTが参加したセッションでの他のギタリストとはどんな関係だったのかな? ラリー・カールトンやディーン・パークス、ルーイ・シェルトンとか。ギタリストに限らないか…ドラマーのエド・グリーンやベースのマックス・ベネットなど白人とのセッションも多かったよね。
U:そうですねえ。ハッキリとはわからないけど面白いところですよね。
D:興味は湧くよね。ギターが複数のときの譜割りはどうしてたかとか。
U:そうですね、リズムのバッキングとリードパートをどういう風に振っていたか…この曲ならオレ、リード取りたいんだよなあとか思ったこともあるかもしれないし(笑)。
D:デヴィッドTは譜面はOKな人?
U:ばっちりですね。自分でも書くくらいだから。自分で書いた曲は譜面もすべて自分で書いていたようです、几帳面な人でいまでも取ってあるので見せてもらいましたが…。
それでも自由に弾くところも多かったと思います、ニック・デカロ盤なんかは基本譜面があったと思うけど、ソロパートなんかはほんとうに自由にやっているのが分かりますね。
バリー・ホワイト*のセッションでもきっちり譜面があったでしょうね。デヴィッド特有のオブリが少なくて単音弾きのバッキングが多かったりするんで、きっと指示どおりにやっていたんでしょうね。
D:ウエヤマ君は、90年代からデヴィッドTを追っていって…戻ってそれこそ60年代からの音をずっと集め、聴いてきたわけじゃない。そのなかで、やっぱりこの時期はベストだったなあと思うことはないの? 対して最近は…なんてことは? いや、意地の悪い質問かもしれないけど、オレはどうもひとりのアーティストをずっと追うことができないたちなんでね (笑)…。
U:うーん、そうですねえ…。キャリアの最初と最近とを較べれば、例えばフレーズの間の取り方が少し変わってきたかなとか思うところはあるかなあ。けれど根本のところはまったく変わってないんですよ、僕の好きなところは。〝ツボ〟ですかねえ…微妙なところなんですけど、メロディの組み立てとか、特徴的なコードの使い方とか、小節に入ってくるときのタイム感とか…。
D:いわば「デヴィッドT節」はキープしているってことか。
U:まだまだ元気ですし、まだまだ聴かせてくれるんですよね…あの節回し (笑)。それとギタリストとして見て、変化が小さい人でもあるかなあ…あまり変わっていない…。だから、今のプレイも見逃せないと思うし、過去の音源であろうがこれからのプレイであろうが、とにかくその音を聴き続けたいって思いは強いですね。
D:じゃあ…ここまで追いかけたからやめられないし、なんて消極的なコレクションとはならないわけだ。
U:ええ、過去盤にしてもまだ聴いてないのがあるはずだって思ってますから。70年代以降の盤はクレジット表記が一般化してくるんで追いかけやすいんですが、60年代から70年代初めの頃ってそういう習慣がまだ定まってないから、プロデューサーやアレンジャーくらいからしかわからないし、そこから辿るしかない。シングル盤なんか特にそうですよね。それがデヴィッドと近しい人脈であればわかりやすいんですけど、そうじゃない場合もある。特に60年代終わりから70年代初めにかけてという時期は、デヴィッドのキャリアが花開くときとバッチリ重なっていて、そのとき周りにいた人たちが、どういう経緯でデヴィッドと知り合って彼を起用するのかっていう歴史的な関係性も知りたいわけです。そういうことを追いかけるうちに、当時のソウルやジャズやロックっていうポップミュージックの裏の部分を誰がどう支えていたのかっていうところが見えてきたりして、そこが面白い。実際、クレジットがなくって知られてない音源はまだまだあるはずです。といっても僕自身はとてもコレクターとはいえないんですけど。
D:それにしては凄い数をチェックしてるじゃない (笑)。
U:人にあげたりした盤もありますから…すべて手元に置いておきたいというのはないんです、あくまで音源さえ聴ければOKなんで…。
D:デヴィッドTは、いくつだっけ?
U:もうすぐ71…ですね。とっても元気です。だからってわけではないけど、今のプレイをまだまだ聴きたいって思うし、一方で、余計にいまのうちにきっちり聞いておくべきは聞いておきたいっていう気持ちもあります。あの頃のモータウンというか音楽界というか、語れるのはもうデヴィッドTぐらいしかいないんじゃないかなあって。スターのことじゃなくてね…裏方がどんなふうに関わっていたかという事ですが…デヴィッドのプレイをただ聴いていたいっていうシンプルな欲求が原点にあるんですけど、それとともに、そういう背景というのか、表から見える風景は違うかもしれないけど、裏では意外なほど人脈的にもつながってたり、あるいは微妙に違ってたり、そういう人たちが音楽の歴史をつくってきたんだという実感が、デヴィッドの仕事を追いかけることでおぼろげながらも感じれるっていう。そこがまたデヴィッドの凄さというか、実際にそれをやり遂げてきたわけですからね。面白いところだし、素晴らしいと感じるところなんです。
D:そこ大事、頑張って〝掘って〟ください (笑)。
【120616 西船橋】