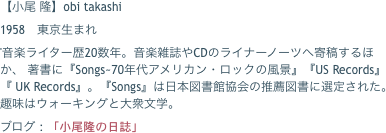 |
||||
 |
||||
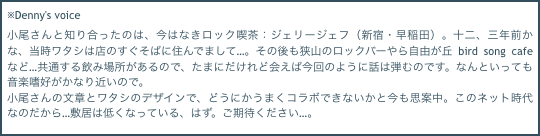 |
||
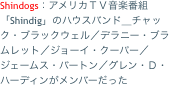 |
||
D(以下Denny):今回、アメリカ音楽に強い小尾さんにあえてお願いした「お題」は〝英国ロック〟ということで…。それもまた面白いかもと思ってなんですが、さてどうなりますやら。
まずお互いの「これぞUKロック」という項目…アーティストだけじゃなくて裏方含め、それを10づつ挙げてみたので見てみましょ。
(Dennyオク山)
Kosh
ドノバン
トニー・ヴィスコンティ
Family
Tレックス
ロッド・スチュワート
ポール・ウェラー
デイヴ・メイスン
クリス・ブラックウェル
Factory (レーベル)
(Obi-One 小尾)
トラフィック
スティーヴ・ウィンウッド
ローリング・ストーンズ
ジミー・ミラー
グリン・ジョンズ
フェイシズ
ジェフ・ベック・グループ
ヴァン・モリソン
グリースバンド
エルヴィス・コステロ
D:『わが70年代UKロック』かと思ったけれど、「ファクトリー」は80年代だし小尾さんの「コステロ」もデビューは… Stiff だっけ?
O(以下 小尾):ファースト・アルバムのリリースが77年の夏です。エルヴィス・プレスリーが亡くなったのがちょうど同年の8月で、それと入れ替わるように偽エルヴィスがバディ・ホリーのような眼鏡を掛けて出て来たという (笑)…。
D:でも活躍はやっぱり80年代だよね。
O:ですね。
D:なので…「70年代」は取って『わがUKロック』で行きましょ。
O:了解です。
D:とは言いながら、最初に言っておきたいのはやっぱり70年代UKロックこそロック黄金時代じゃないかという… (笑)。
O:まさにそうでしたね。
D:なかで、ELP (Emerson, Lake & Palmer) やクリムゾン (King Crimson) などはプログレッシヴロックというジャンルで括られて「様式美」とよく言われていたけれど、オレは…あれは単に使っていたシンセという楽器の共通項だけでやっていたことは様々、別々だったように思うのね。
O:なるほど。
D:それよりもいわゆるUKロックバンドのほうが、ベース/ギター/ドラムが基本のロック様式美だったように感じるなあ。ギター・オリエンテッドとも云えるかな、ハモンドやエレピのキーボードも入ったけれどギターとヴォーカルに重きがあった様式美。ストーンズ、フリー、フェイセス、クィーン…。カッコイイもの、今日まで続く「ロック」の代表というイメージを持ってますね。そこら、小尾さんとしてはどうですか?
O:それは分かりますね。ただ僕の場合、ギターって好きだけどいわゆるギターヒーローを崇拝するような聴き方はしてこなかったですね。
D:分かる分かる。小尾さん、それないよね。
O:それよりもリズムギターの面白さに気づき始めたから、あくまでリズムを中心に聴いてきたかな…8ビートが16ビートになる面白さも同時代的に聴いてこれたし、逆もありでスウィングビートとか4ビート、ロカビリーっぽいのもありましたよね。やはりチャック・ベリーが大前提というところからギター弾きを見るような癖が僕にはあります。
D:そうだなあ。派手な速弾きよりもギターのアンサンブル…。
O:間の取り方…。奥山さんも僕とほぼ同じ感覚だと思うんですが、シングル・ノートをバリバリ弾き倒すというよりはオブリで何気なくいいフレーズをちょこっと小出しにするギタリストがいいなあと思うわけで、そういう意味では僕の場合はロン・ウッドがリズム・ギターの鑑ですかねえ。あの人はソロを弾いていても途中でフレーズが手詰まりになると、すぐカッティングで誤摩化してしまう…。そういう部分も含めて、もう「あばたにエクボ」的に好きですね (笑)。
D:ギターだけじゃないか、リズムを作ってゆくバンドのうねり、今風にいえばグルーヴかねぇ…そういうのに惹かれて行ったよね。
O:シンプルなロック編成のバンドに惹かれつつ、やっぱりアメリカを意識しているブリティッシュバンドなんかに1番しっくりきたのかなあ。
D:UKバンドといってもアメリカ音楽の影響は絶大だしね、ブルースもR&Bも…。そのなかにイギリスのエッセンスが混じるところが魅力でね。ファミリーなんかもそうだけど、どこかシアトリカル=演劇的じゃない。シェイクスピアの国 (笑)。
O:ありますね、それ (笑)。
D:それとシニカルさ。ハスからの目線というか。どこか皮肉っぽく諧謔的なのは単純なアメリカンとは違う (笑)。
D:さてと、どこから行きましょ。え〜まずこの(挙げた)名前の中で、小尾さんの「トラフィック」「スティーヴ・ウィンウッド」とオレの「デイヴ・メイスン」がひと括りだよね。そこに「クリス・ブラックウェル」… Island レコードとしてこの名前も絡みだな。
あ、その前に…小尾さんは「スティーヴ」派なの? オレは「スティーヴィー」でしかないんだよね、スティーヴィー・ウィンウッド。スティーヴではどうにも座りが悪すぎる (笑)。
O:なるほど、僕もスティーヴィーですけどね。《good bye Stevie》って曲もありましたしね。
D:キース・リチャーズ…これもない。最後の[s]はないぞ、あくまでリチャード!とか (笑)。どうでもいい余談です… (笑)。で…古いところ、クリス・ブラックウェルから始めましょうか。
O:はいはい。
D:ブラックウェルがアイランド(レコード)を始めたのって何年でしたっけ?
O:64年…ごろでしたかね。
D:まずは♪ロリポップロリポップ〜…ミリーだっけ、《my boy lollipop》で当てた?
O:ですね、それが64年です。
D:この人、白人で…ジャマイカ育ち。後にボブ・マーリーを世界的なビッグネームまで押し上げた仕掛け人だけど、最初のミリーからしてそっちのサウンドでしたね。
O:スカですね。
D:他のカリブ諸国がフランス領だったのにたいしてジャマイカはイギリス領、「英語圏」という意味で…こと音楽だけでみればツキがあったのかもね、イギリスへの移民がカリブ音楽を持っていってブルービート/スカ/レゲエまで、すんなり溶け込んだわけだから。支配される側の苦悩という側面をひとまず置いておいての話だけど…。
O:まあその英国におけるカリビアン音楽のナンバー1仕掛け人としてブラックウェルがいたわけですよね。
ブラックウェル自身がジャマイカで青年時代を過ごしているんですね。思い入れももちろん相当なものだったでしょう。
D:だいたいレーベル名が〝アイランド〟って、その拘りたるや…ですな。
ブラックウェルが知らしめたモノってのはある意味〝リズム〟でしょう。一般聴衆はもちろん、プロのミュージシャンらにもかなり新鮮なモノだったんじゃないかなあ。その初期にレーベルに所属したのが、かつて兄ちゃんと一緒にスペンサー・デイヴィス・グループでUKバンドの典型のように活動していたスティーヴィ・ウィンウッドが、その後結成したのがトラフィックだったというのも面白いところで…。
O:ただスペンサー・デイヴィス・グループに戻ると彼らは Fontana レーベルだったんだけど配給はアイランドだったんですよね。
D:あ、そうなんだ。
O:なので実質クリス・ブラックウェルの息はかかっていたわけで、バックコーラスにミリーが入っていたりスカ・ビートっぽい曲も演ってましたね。Jackie Edwards の《keep on running》も採り上げていました。
スペンサー・デイヴィス・グループの後期ごろからジミー・ミラーもからんでくるんですよね。
D:早くも登場でしたか…。
O:ジミー・ミラーはアメリカ人で、NYの生まれかな。クリス・ブラックウェルに見込まれて渡英したという経緯があります。パーカッシヴな音作りが得意だったというでしょう。《gimme some lovin' 》のUKヴァージョン/USヴァージョンの違いをご存じですか?
D:いや知らない。
O:USヴァージョンは派手に鳴り物/パーカッションをたくさん入れてるんですね。UKはシンプルなまま。《I'm a man》や《waltz for Lumumba》でも大胆にパーカッションを取り込んでいます。
D:それはジミー・ミラーがUSヴァージョンを手がけた?
O:そうなんです。トラフィックも最初の2枚がジミー・ミラー・プロデュースなんでね、そういう音作りは活かされてるなあと…。
D:トラフィックはその後にアフリカからの Reebop なんか加入させて…。
O:ガーナ出身の人ですよね。
D:どんどんパーカッシヴになってゆくけれど、ジム・キャパルディはそれにともなってドラムをたたかなくなっていったね (笑)。
O:最後はタンバリンだけとか (笑)。
D:あの人は基本、歌いたかったんだろうなあ。ソロも何枚も出したし。もっとフロントに立ちたかったんだね。
O:あの人のジョー・コッカーっぽい歌い方って、好きだなあ…。
D:オレもそうです。ソロはマッスル*録音が多かったからそこらを軒並み買って聴いたんだけどハマりましたワ。
O:でもトラフィックを引っ張ったのはウィンウッドであり…彼は、早期にブラックウェルの影響もあっただろうし、ジャマイカやアフリカのリズム/ビートに目覚めて単純な8ビートじゃない世界にハマったという感じかな…グルーヴ感、曲も長尺になっていって。ポリリズムの気持ちよさかもしれない…イギリスでの事なんだけど、逆にそういう第三国からの影響がまたイギリスらしさだったようにも感じますね。
トラフィック自体が最初のバンド形態から次第にウィンウッドのためのユニットのように変化していきましたね。象徴的なのは〝On The Road〟というツアーのためにマッスルショールズのリズム隊をまんま雇い入れてしまったこととか…。
D:あれも不思議だったね、固定のスタジオ付きのメンツのはずがワールドツアーを廻ったわけでしょう。こんどはアメリカ南部勢のグルーヴまでも取り込んだ…。
トラフィックにはジム・ゴードンも参加盤があったね。まあクラプトンとも通ずるところなわけだけど、ある時期からアメリカ南部サウンドの英国での…「流行り」だったんだろうなあ、始まったよね。
そこで出したい名前がデイヴ・メイスンなんですよ。メイスンて…グラハム・ナッシュのほうが先?、でも印象では最初に西海岸へ渡ってまでアメリカ音楽にどっぷりハマったアルバムを出した英国ミュージシャン、先駆的な位置にいたでしょ、あの時点で。
O:メイスンの【alone together】*はクラプトンの最初のソロより数ヶ月早いんですよ。
D:あのソロで、デラボニ人脈/レオン・ラッセル勢…最高の南部ミュージシャンをバックにして曲もいいし、イギリス勢が目覚めたUS南部サウンドを最高の形に、それをファーストにして作ってしまったメイスンだったという意味で重要な名前なんだけどな。ただその後の冴えの無さもまたメイスンらしくて捨てがたい… (笑)。
O:彼のトラフィック時代の代表曲が《feelin' alright》ですよね。ジョー・コッカーもファーストアルバムでカヴァーしているし、面白いのはルル…マッスルショールズ録音の【new roots】でやってますよね。この曲のミディアムで跳ねるようなグルーヴ、象徴的な感じがしますね。あと面白いのはこの曲、ストーンズの《無情の世界/you can't always get what you want》にそっくりなんです。両者ともにパーカッションが入った横揺れビートになっているし、《無情の〜》ではチャーリー・ワッツではなくジミー・ミラーがドラムスを、ロッキー・ディジョーンがパーカッションを叩いているのが何とも興味深いです。
D:アメリカ南部サウンドはかっこいいぞと言っているようなタイトルだしなあ…。しかしそうなると同時期にウィンウッドもそう感じていたはずだから同じ土俵でやっててもよかったはずなのにねぇ…。やっぱりルックス面でもウィンウッドと一緒にいるのは嫌だとメイスンは思っていたのかな (笑)。
O:フフフッ (笑)。案外そんなところがあったのかも。トラフィックの曲でいうと、メイスンは単独作品だったけれどウィンウッドは、キャパルディ=ウィンウッドのコンビで作ってましたね…そこら辺もなにかあったかなあ。
D:クラプトンがその後、マイアミのクライテリア*を拠点として南部ミュージシャンをバックに従えて活動していったけれど、ほんとその先駆的存在としてのメイスンはもっともっと評価されてしかるべき…なんてね、オレはヒイキなんで思うわけですヨ (笑)。
O:《only you know and I know》でのドラムはジム・ゴードンの手癖が出ていてカッコいいですよね。
D:ジム・ゴードンは…デイヴ・メイスンありきトラフィックありきで、ドミノスではクラプトンと…。英国勢に貢献していたなあ。
O:マッド・ドッグズ&イングリッシュメンからですから、あそこではゴードンとケルトナーと…もうひとりいたかな、凄いメンツでしたね。ケルトナーにしても僕らが意識し出したのはマッド・ドッグズやデラボニ盤からですね。
D:レオン・ラッセルも、ジョー・コッカー(のバック)をやって当てたからロックのフロント・シーンへ出てこれたんだよなあ。あのメンツって、もちろん南部勢なんだけど、活動の場所はロスだったでしょ。みんなで Shindogs* としてTVへ出たり、レッキング・クルーとしての活動…いわば糊口を凌いでいたってことだったんじゃないですか。それが英国へ渡って大注目された…。それは、レオンと共同で Shelter レーベルを興した…誰だっけ?
O:デニー・コーデル。
D:そうそう、コーデル。イギリス人、もともとムーディー・ブルースとかやっていた人でしょ?
O:ムーディー・ブルースやジョージ・フェイムのマネージメントやっていた人ですね。ジョー・コッカーを発掘した人でもあった…。
D:そのコーデルがかなりキー・パーソンだったんだろうな、どこでレオンと絡み始めたかは分からないけれど南部勢の英国進出の裏にはコーデルがいた…。
O:レオンのファーストはオリンピック・スタジオ録音でしたよね。たしかジェシ・デイヴィスのファーストもオリンピックでグリン・ジョンズがらみだったかな。
D:そこはいろいろと絡むんだよなあ…。ボビー・ウィットロック盤もジミー・ミラーのプロデュースでUK録音でしょ。軒並み英国録音でさ。それが可能だったのも彼らアメリカ勢がイギリスで注目された、セッションに駆り出されて名が売れたからだよね。
O:ケルトナーでいえばジョージ・ハリスンに起用されたのも大きかったですね、【バングラディシュのコンサート】あたりから。
D:ジョンもあったでしょ、【imagine】からやってるし。…いくらライ・クーダーのところでいいタイコ叩いていても、それだけじゃ喰えないわけで、やはりビートルズ人脈というのはケルトナーにとって大きかったんだろうね。ジェシ・デイヴィスもジョンのバックはいろいろあったね。《stand by me》では素晴らしいソロ…。
O:ジェシ・デイヴィスが認められたのはストーンズの『ロックンロール・サーカス』からでしょうけど、それはその前年67年にロスの Whiskey a Go-Go でのタジ・マハールのステージをミック・ジャガーが見ていたかららしいです。そこで気に入ってあの番組への出演を依頼した…。
D:タジはインテリだからブルースの解釈が真新しい…ミックが惹かれたところかも。