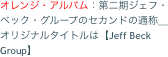 |
||
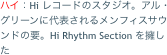 |
||
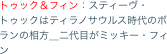 |
||
D:グリン・ジョンズ…いきましょうか。グリンてオリンピック・スタジオのハウス・プロデューサー?
O:そうですね、オリンピックを代表するプロデューサーですから。
D:イギリス人?
O:あの人はイギリス人。
D:で、弟が…。
O:アンディ・ジョンズ。
D:グリン・ジョンズも英国ロックのビッグネームなわけだけど…小尾さん的にはグリン作品としてまず出てくるのは?
O:え〜と…【Who's next】…それと【馬の耳に念仏】かなあ。【ウー・ラ・ラ】も。面白いのは【let it be】のエンジニアもグリン・ジョンズじゃないですか。それとスティーヴ・ミラー・バンドやイーグルスというアメリカ勢も出てくるんですよね。
D:イーグルスは…最初の二枚だっけ?
O:そうです、オリンピック録音で。
D:ストーンズとはどういう関係?
O:デビュー当時から関わっていたようですね。ただクレジットされない時期が続いていたらしく…。エンジニア仕事は多くてもプロデューサーとしての名前が最初に出たのは【get yer ya-ya's out】ですね。
D:オリンピックというスタジオの名前が英国ミュージシャンのなかで大きかったのかもね、あれだけのアルバムが録音されたんだから。
O:う〜ん、そうですねえ…スタジオといえばオリンピック…それとトライデントですかねえ。
D:オレのなかでもフェイセス=オリンピック=ジョンズのイメージかな。そこで、小尾さんがフェイセス、オレはロッド・スチュワートという名前が出てくるわけだけど。ロッドはジェフ・ベック・グループでもあったか。じゃそこから聞きますが、このジェフ・ベック・グループはロッドがいた第一期?
O:ロッドがいてニッキー・ホプキンスがピアノで入って、ロン・ウッドにミック・ウォーラー…第一期が好きなんですけど、それ以上に第二期が好きになりましたね (笑)。「オレンジ・アルバム」*でスティーヴ・クロッパー・プロデュース、メンフィスのアーデント・スタジオ録音ですよね、この盤が印象的で…ギターヒーローの時代にベックはやっぱりアメリカ南部を押さえていたよなあという感が強いんですね。ドン・ニックスにボブ・ディランそしてスティーヴィ・ワンダーの曲をやっていて…。さらにその後のベック・ボガード&アピスではインプレッションズの《I'm so proud》までカヴァーしています。向いている方角はもう完全にアメリカですし、しかもギター指向というよりはソング・オリエンテッドな方向性を目指していましたからね。
D:結局ベックもアメリカかよ…とか (笑)。どんだけアメリカ南部音楽が好きやねん、あんたらは…英国勢に言いたくなるよね (笑)。それでも、アメリカ大好きは分かるけれど…やっぱり英国人というルーツは感じさせる…そこがまた魅力。ある意味しつこくロッド・スチュワートを聴いてきたのもそこらなのかなと自分で思いますね。
アメリカ音楽の大雑把な魅力を吸収しつつも細かく解釈して音を紡ぐ感じかなあ、英国らしさって。それは逆にアメリカ人には通じないんじゃない? 同じ島国日本人のほうが分かってる… (笑)。
O:意外なのはヴァン・モリスンとロバート・パーマーにマッスルショールズ録音がないことなんですよ。どちらも行ってておかしくないはずなのに…。
D:あ、それあるね。
O:もしもビートルズの解散が2年遅れていたらマッスルショールズへ行ったんじゃないかって思いがありますよ。【let it be】ってどこか土臭いところがあるじゃないですか、ならば次のロケーションとしてマッスルという選択肢も有りだったんじゃないかなってことですよね。
D:ビートルズも南部か (笑)。
O:その部分でいえば、四人のメンバー以外のプレイヤーが本格的に絡んだのがビリー・プレストンでしたからね。【let it be】のセッションでいえば、ジョンの《don't let me down》なんかもろサザーン・ソウル〜ゴスペルの世界で、当時これは今までのビートルズとはちょっと違うぞ! と漠然と子供心にも感じ取っていました。
D:もろゴスペルなキーボーディスト、十分に南部な人だったわけか。
O:イギリス勢にあれだけ支持されたレオン・ラッセル&シェルター・ピープルですけど、いわゆるゴスペルの〝コール&レスポンス〟をうまく取り入れていましたよね。
D:イギリス勢は、ガキん時にただ好きで聴いていたアメリカ音楽が実は南部的、ゴスペル的なものだったと再認識させられたのかもしれない。ブラックベリーズ*のお姉さんらがイギリスでも受けたけど、そこらとリンクしてそう…。
O:アイク&ティナ・ターナーのジ・アイケッツとか、レイ・チャールズのザ・レイレッツとかがコール&レスポンスの雛形として焼き付いていたのかな? それでレオン・ラッセル&シェルター・ピープルも、ハンブル・パイ&ブラックベリーズも、彼らがやりたかったことを説明出来ちゃう (笑)。
D:ちょっと戻ってフェイセス…いやロッドだな、大好きなロッド・スチュワートを語りたい気分なんですが、酔いのせい? (笑)、いいスか?
O:どうぞ (笑)。
D:ロッドは、元来のアメリカ大好き人間として75年に【atlantic crossing】で堂々と宣言したわけでしょう、海渡ったからねと。今日からアメリカ人、ハリウッド人じゃけんな〜そこんとこヨロシク!と (笑)。あの潔さは凄いなとも思うわけです。
O:そうです、あのジャケで開き直ってますよね、凄い。
D:でもイギリス捨てたかというとそうでもないんだよねぇ (笑)。自身で、実にスコティッシュらしい Riva Records ってのを興して英国配給はやっていたしね。渡米前の【never a dull moment】【every picture tells a story】なんてのは英国ロックの神髄、ベストと数えられる名盤でしょ。それがあって、でもアメリカ渡ってマッスルやらハイ*でも…ベースはロスにして実にアメリカンテイストなレコードを制作してる。でもマンフレッド・マンの曲もやる…。アメリカ大好き、でもイギリスも有りヨみたいな、ぐちゃぐちゃなところ…OKです、好きなんです (笑)。
O:なんか分かるなあ (笑)。
D:ロッドは、たぶんロック・ジャーナリズム的には《do ya think I'm sexy?》のディスコ路線で「抹殺」されておりましょうが (笑)、わたしゃあのアルバムにも好きな曲はあるし、その後【foolish behaviour】【tonight I'm yours】…【body wishes】、ここらまでOKなんですよ。
O:あ、そうでしたか、意外ですねえ、奥山さんがそこまで追っているのは知らなかった。
D:アルバム【foolish behaviour】のB面、ここに3曲のバラードがあるんだけどこれがたっまらなく!…好き。数多くロッドは聴いているけれど、最良のパートじゃないかな、あれは。どれもオリジナル楽曲でストリングスがデル・ニューマン…録音はロスなのにこのストリングスは実に英国気分でね、これが最高。
O:デル・ニューマンて、ポール・バックマスターがらみじゃなかったでしたっけ?
D:どうかな、オレの知るところではドノバンやキャット・スティーヴンスなど。イギリス人ストリングス・アレンジャーだよね。あ、ここでヴィスコンティが出てきちゃうか。オレ、弦が大好きでさ…ポール・バックマスターもいいね、けれど一番はトニー・ヴィスコンティ。
O:バックマスターはエルトン・ジョンですね、《madman across the water》なんか重厚なストリングスがほんと英国的ですね。ヴィスコンティというのは奥山さんとしてどういう存在ですか?
D:バックマスターは…その重厚さが魅力でもあるけれどちょっとクラシカル過ぎるという気がするんだ。英国王室音楽院て感じじゃない (笑)? そこいくとやっぱりヴィスコンティ。ヴィスコンティは世界で一番「ロックな弦を書ける」アレンジャーと思うのですよ。プロデューサーとしてのヴィスコンティはいろいろなミュージシャンとからんでいただろうけれど、オレ自身はそんなに追いかけていたわけじゃないのね。Tレックスとデヴィッド・ボウイ…ぐらい。なかでもTレックス、やっぱりTレックスこそヴィスコンティだ〜ね。
O:Tレックスの曲でイントロからガツンと弦で始めたり…凄いですよね。
D:弦を書くって、当たり前にクラシックなお勉強を幼少期からやっていたような人たちしかできないよね。当然クラシカルなんだ…どの弦も (笑)。ヴィスコンティもその名前からして相当な家系の出身と思うけれど、でもその弦はほんとロックスピリットに溢れてるんだよなあ。とくにTレックスでね。オレにとってTレックス…その前のティラノサウルス時代も含めてもそうだけど…Tレックスとはマーク・ボランとトニー・ヴィスコンティのタッグ・ネームと思ってるから。スティーヴ・トゥックやミッキー・フィン*はほとんど関係ない、8割方「トラ」という認識です (笑)。
O:なるほどなあ…。
D:ボランの曲、そしてあのヴィブラート・ヴォイス、そこに被るボトムの利いた弦!
O:まさにボトムですね! 余談ですけどボランの奥さんはグロリア・ジョーンズでしたね。
D:アメリカ人、黒人で。やっぱりボランも南部志向か? (笑)
O:みんなそうなっちゃいますね (笑)。 ヴィスコンティといえばラルフ・マクテルやバート・ヤンシュの盤もやってるんですよね。
D:戻りますけど第二期ジェフ・ベック・グループの魅力って何ですかねえ?
O:よりファンクになっていった事じゃないですけねえ。ギターヒーロー的なプレイよりもベックのギターもアンサンブル重視で…。マックス・ミドルトンのキーボードも色気があってねえ。
D:そうそう、いいよねえ。
O:ボブ・テンチのヴォーカルも、ちょっと気張り気味なんだけどそこもまた良し… (笑)。
D:ベックが抜けてハミングバードへ流れていったけど、コアになったのはミドルトンのキーボードだよね。このキー・パーソンがいなかったらジェフ・ベック・グループもなにも無かった (笑)…かも。
O:キーボードプレイヤーって全体を見渡す役割を担ってますよね、ミドルトンもまさにそこらが分かっている奴だな、と。
D:キーボードって楽器を扱えること自体がまあ〝いいとこの出〟でしょう。ギタリストみたいにガツガツしないんだね (笑)、引く所出る所、己をわきまえてる。
(夕方5時に始まったトークは酔いも手伝ってか、いつの間にか気がつけば4時間近くもの果てない音楽談義へと (笑)…)
D:なんか酔いながらグダグダきちゃったねぇ〜 (笑)。
O:長くなりましたね、まとめるの大変じゃないですか?
D:う〜ん、…だねえ (笑)。でもまあ適当に。
O:だいたい挙げた項目は喋ったんじゃないですかねえ。グリースバンドとコステロが残ったかな。でもグリースバンドもジョー・コッカーの残党だから…。
D:リリースはシェルターからだっけ?
O:アメリカはシェルター、イギリスではハーヴェストですね。
D:グリースバンドも…パブロック・サーキットになるわけ?
O:解散後にヘンリー・マックロウがフランキー・ミラーやロニー・レーンのバックをやったというキャリアから遡ってバンドもそう取られるようになったかなあ。
D:あれ? ジミー・マックロウ…こっちは…ストーン・ザ・クロウズ?
O:ですね、マギー・ベルと。
D:《my love》が…
O:あれはヘンリー・マックロウの名演奏ですね。ややこしいのはその後にウィングズにはジミー・マックロウも加入したから…。ジミーはサンダークラップ・ニューマンもありましたね。ピート・タウンゼント・プロデュースで…。
D:【hollywood dream】だっけ。
O:あのアルバムこそ、アメリカ憧れの英国人制作の傑作ですね。
D:ここまでの喋りはそこに尽きる感じだよね…アメリカ大好き英国ミュージシャンのなんと多いことよ (笑)。でも出自は隠せないというか、英国気質が見え隠れ。
O:じゃあそれがまとめってことで…? (笑)
D:焼酎もなくなったからそろそろ締めますか…。
【120917 池袋・餃子楼】
【Denny 追記】
Factory については触れられなかったので一言…80年代に入ったUKは各地でインディペンデントなレーベルが活況を呈した。インディーというとまずグラフィック的にショボいという印象を持つだろうが、ことこの時代の英国インディーは揃って!…すばらしいグラフィックであった。なかで 4ad レーベルのジャケを手がけたヴォーン・オリヴァや Rough Trade / Fetish レーベル・ジャケで活躍のネヴィル・ブロディなどはアート作品といっても過言でない傑作を数多く産み、その名は世界的に知られる存在となる。
マンチェスターでトニー・ウィルソンによって創立されたファクトリー・レコードこそグラフィカルに最も優れた統一を見せたレーベルだった。そのほとんどはピーター・サヴィルという類い希な才人によるデザインである。ジョイ・ディヴィジョンを世に送り出したレーベルは、音像とヴィジュアルが見事にマッチしていた。