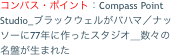 |
||
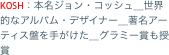 |
||
D:ここでミックの名前が出てきたところで、聞きたいのは小尾さんが入れた「ローリング・ストーンズ」…ストーンズは活動が長いけれど、あえてここでストーンズを入れたのはどういうところから?
O:え〜と、Reebop の話がありましたけど、同じガーナ出身のロッキー・ディジョーンが《悪魔を哀れむ歌》でパーカッションを叩いてますよね。音楽的な幅が広がりつつあった時代にストーンズもやっぱり目を向けていたという事実があります。ウィンウッドのトラフィックともリンクするし、メイスンは【ベガーズ・バンケット】にも参加してますね。
D:【ベガーズ・バンケット】のプロデュースって?
O:このアルバムからジミー・ミラーとストーンズとの蜜月時代が始まります。何でもトラフィックの2枚めを聴いて気に入ったミック・ジャガーが、ミラーに直接交渉しに行ったらしいんです。レコーディングも同じ68年に【トラフィック】と同じオリンピック・スタジオ。そんな符合がありますね。
D:そうか、もうジミー・ミラーはからんでくるのか…。話は繰り返しだね (笑)。ストーンズもリズムのうねりに目覚めて、アメリカ南部もどっぷりに変化していった…なにしろマッスル録音で《brown sugar》録ってるバンドだしなあ。
しかし今思えばブライアン・ジョーンズ…アルバム【ジョジューカ】をして最初にアフリカンポリリズムに注目したのはこの人かもしれないね。
O:そういえば、そうですねえ。ブライアンがモロッコまで旅して現地の部族の音楽をテープに録ってきたという作品でしたね。ウィンウッドは73年にレミ・カバカやオシビサの人と三人でサード・ワールドっていうアフリカ音楽のユニットを組むんですが、やはり【ジョジューカ】にはかなり影響を受けたと思う。
D:ミック・テイラーはどうですか? もちろんストーンズは60年代からカッコいいバンドなんだろうけど、まあリアルタイムって意味でもね、70年代ストーンズこそ黄金時代という気持ち…それはキースとミック・テイラーの絡み合いがあってこそというのがオレのストーンズ感なんですがね。
O:僕は、ミック・テイラーの一番の名演奏は《all down the line》と思うんですよね。スライドの印象が強いなあ…メロディックで濁らないスライドね。
D:オレは《time waits for no one》でのプレイが最高に好きだなあ。
O:なるほどね。《silver train》でもいいギター弾いていたなあ…。
D:小尾さんの挙げたジミー・ミラー、この名前もたしかに重要な位置だよねえ、ブリティッシュロック…それもアメリカンテイスト…かな。 ミラーはアメリカ人でしたっけ?
O:そうです。もともとパーラメントに関係していたようです。最初期でまだパーラメン「ツ」であった頃に…。戻りますけど、クリス・ブラックウェルに気に入られてイギリスに渡って活躍し出した…。
D:あ、そう。意外な所から始まっていたんだ、知らなかった。クリス・ブラックウェルは…コンパス・ポイント*を作ったときに仕切り役をまかせたのがアレックス・サドキン。このサドキンはもともとクライテリアのテープオペレイターだった人でね、ブラックウェルはアイランド制作盤としてかなりの枚数をマッスルショールズで録っていたからマッスルとは関係深いクライテリアへも何度も足を運んでいたんだろうと…。
そこら辺てのは、英国レーベル=アイランドもやっぱりアメリカでの成功こそが真の成功という戦略もあったのかも…。
O:イギリス人て、アメリカで成功してなんぼのモンという意識は強いんですかねえ?
D:単純にキャパとしてマーケット規模として、イギリスはさほど大きくないよね。今、韓国勢が日本へ進出するのと一緒だろうなあ。同じCD出すんなら大きいマーケットで売りたいと思うのは当然だし。音楽的な志向から本場アメリカで認められたいという純粋な気持ちもミュージシャンとしてアリとは思うけれど…。ブリティッシュ・ロックの典型だったフリーなんかにしても、末期にはテキサス出身のラビットをメンバーに入れたり、フリー解散後のポール・コゾフはアメリカ人たちと Back Street Crawler を組んだりね。やはりいつもどこかアメリカを意識している部分があったと思う。
O:マーケットと音楽志向、それは両方でしょうね、気持ちの部分とビジネスの割り切り…微妙にからんでのことですよね。フリー解散後にポール・ロジャーズがバッド・カンパニーを組んでアメリカで大成功したのはすごく象徴的ですね。フリーでは《all right now》しかアメリカではチャートインしていないんだけど、バドカンは全米トップ40に喰い込んだシングルが6曲もある! この違いは大きいですね。ロジャーズとドラッグで亡くなったコゾフとで残酷にもフリー出身者の光と陰になっているというか…。あとさっきのカリブ海の話じゃないんですが、フリー末期にロジャーズはトゥーツ&ザ・メイタルズのトゥーツ・ヒバートとセッションをしているんです。まあこれは未発表に終わってしまったんですが、これまたアイランド・レーベルらしい逸話だなと思って。
D:そこでね、オレは挙げた中からポール・ウェラーの名前を出したいんですけど…。というのは、ポール・ウェラーってアメリカじゃぜんぜんダメじゃないスか。そこがね…イイのよ (笑)。ひじょ〜に英国的な立ち位置、美意識…それが素晴らしく好きなんです。
O:なるほど (笑)。
D:ジャム時代はほとんど思い入れなくて専らスタイル・カウンシルのファンだったんだけど…。UKモータウン・サウンド的なところから始まってカーティス*も有りで、とことんアメリカ音楽に傾倒しつつもやっぱりシニカルな英国気質かなあ。そこにフレンチの香りもまぶせてユーロ的とも云えた (笑)。スタイル・カウンシルってのはウェラー/タルボットのふたりのユニット名というよりもまさにスタイリッシュ=美意識のアイコン名じゃないですか。これ、ぜったいにアメリカ人には通じないと思った! (笑)
同じ島国としてイギリス/日本は共通項というか近いメンタリティがあると常々感じるわけです。日本人の英国ロックへのシンパシーも相当なモンなんじゃないかってね。
O:まさにそうですね。何しろグループ名が〝スタイル評議会〟ですからね (笑)。ウェス・モンゴメリー的なギターもあれば、タルボットはジミー・スミスのようなハモンドB3を弾くという五目飯状態でしたね。【our favourite shop】に写っているレコード・ジャケットの元ネタを探したり、ヴァージョンが違う12インチの《my ever changing moods》を買ったり、僕もしました。
D:そこで、ファミリーも出さないとだめだな。ここもアメリカ人に通じない世界…シアトリカルな英国ロックの粋みたいなバンド。哀愁のメロディを歌うしゃがれたロジャー・チャップマンのヴォーカル…これぞロックヴォーカルでしょって、オレなんかつくづく感じるわけね。
O:あの声を活かすんだったら、凡人だったらもっと直球勝負なアレンジで行きますよね、そうではなくて一筋縄ではいかない展開へもってゆく (笑)…不思議な魅力のバンドでしたね。ジェスロ・タルにも近い演劇的な世界も…。
D:ファミリーってチャップマン=チャーリー・ウィットニー、ふたりのユニット名。他のメンバーは常にトラ*。ジョン・ウェットンの一応はデビューバンドですよね。ロッド・スチュワート・バンドの要になったギタリスト、ジム・クリーガンがいた時期もあった…。
そこでもうひとつ、挙げたなかから KOSH *も絡むわけですよ。
O:コッシュですね。
D:はいはい、ワタシの大好きなジャケット・デザイナー…もう天才的ですがね。ざっとたどるとアップルのデザイナーとしてビートルズの【abbey road】【let it be】のデザイン。ジョン&ヨーコ盤、メリー・ホプキンス、ドリス・トロイも…。それでもずっとフリーランスだったと思いますよ、ストーンズは【get yer ya-ya's out】。【Who's next】もコッシュのデザイン。信じられなく大物盤を手がけたデザイナーですけど、本領発揮はけっこうマイナーな仕事だったりするわけで…、なかでファミリー盤では傑作ジャケばかりなんですよ。ジム・クリーガンの当時の奥さんだったリンダ・ルイス盤も手がけている…。
O:そうですね、【Lark】はコッシュでしたね。
D:そのクリーガンがロッド・バンドへ移った時期、ロッドのジャケも手がけていたところからしてもコッシュとファミリーの付き合いはかなり深かったように想像するんですヨ。
O:なるほどねえ。
D:コッシュはその後ロサンゼルスへ拠点を移してほとんどアメリカ人のような活動へ変わった人だけど、英国時代の仕事は…いや、ロスへ行っても英国アーティストもやってますけどね…、やはり英国人だなあと思わせる繊細さもあってね、いいんです。アーティストに近い人だったろうなあ、それでなければあれだけ多くのミュージシャンの盤をやれるわけない。挙げたなかではドノバン/ファミリー/Tレックス/ロッド・スチュワートのジャケットをやってます。
O:ドノバンはどこらですか? 【essence to essence】?
D:そうです。その前の【cosmic wheels】、【live in Japan】も。
O:え? 【live in Japan】もコッシュですか。そうなんだ…。
D:はいはい。で、ドノバンに移ると…名前を挙げたなかで最初にミュージシャンとして出てくる、英国ミュージシャンといって個人的にイの一番に挙げたくなるほど好きなのがドノバンなんですワ。60年代の、まあヒット連発したミッキー・モストの仕切り時代は…もちろんきらいじゃないんだけど、もうちょっと後…吟遊詩人然とした《wear your love like heaven》《アイレー島》《ラレーニャ》なんかの時代がドップリ…なんですね。まあ兄キの影響なんだけど。遠藤賢司好きだった兄キがその流れでドノバンも買いだしたからそれを聴いて…。
O:《wear your love like heaven》や《sailing homeward》なんか凄くいいですよね…。
D:アコギ一本でもフォークじゃないぞ_どんなにスローでメロディアスで美しいアルペジョであっても心はロック、ドノバンはロック…そういう思いはあったなあ。そうだ、ドノバンも西洋音階だけじゃない不思議メロディを早くから書いていた人だったね。
O:シタールも早かった人ですよね。
D:そうでした。…シタールって誰が最初にロック的に弾き出したんだろう?
O:う〜ん、それは分からないけれど、イギリスにはインド人も多かっただろうから…。やはり《黒く塗れ!/paint it black》でのブライアン・ジョーンズが最初なのかな。それからジョージ・ハリソンへと。デイヴ・メイソンは初めてジョージの家に遊びに行った時、発売前の【サージェント・ペパーズ〜】を聞かされて、そこでシタールを手にしたそうです。それがトラフィックのファーストでの《utterley simple》に結び付いていくという…。
D:そうだそうだ、ロンドンにはインド人のコミュニティはずっとあっただろうね。
O:そこら、ちょっと大げさに言えば征服した側の負い目みたいのってどこかあって…マイノリティな移民コミュニティにシンパシーを示すっていう側面、あるんじゃないですかね。